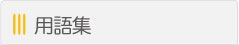エロス |
|---|
| エロス(eros)と聞くと、すぐエロビデオ、エロマンガなど、セックスを題材とした作品世界を思い浮かべる人が多いことでしょう。言葉が、転用につぐ転用をされていくうちにそうなったのですが、もともとは古代ギリシャ語で「エロース(Έρως)」とは、親近感のある愛、受苦(パスシオン)として起こる愛を意味し、やがてそれが神格化されて恋心や性愛の神の名となりました。 フロイトは、人間にとって性とは、なにも性器の挿入や交合だけをいうのではなく、それが日常生活の多くの領域に象徴的にいきわたっていることを指摘し、エロスをもっと幅広い言葉としてとらえ、人が人生をいっそう味気のあるもの、生きるに値するものとして創造していく欲求である、と考えました。 たとえば、近年に流行しているスードク(数毒)というパズルは、およそエロティックな行動とは考えられません。しかし、それにはまりこむ人は、寝食も忘れ、もちろんセックスしたいとも思わず、ひたすら数字をあてはめている状態にあります。そうしたときに、「その人はエロスをスードクに向けている」ということができます。 もっと身体的なエロスのあらわれ方の例としては痛みが挙げられます。 「ハ・イ・ジ」が依存症者の回復の入り口にあらわれる典型的な自覚症状であるように、身体のあちこちの痛みは、その人が意識しないままに、エロスを依存対象ではなく、自分の身体へ向けるようになった証しでもあります。つまり、痛みもエロスの産物であるわけです。 また、夫との性交渉がなくなった妻が、息子の世話焼きに血道をあげているときには、たとえ母子近親姦のような直接の性交渉が息子とのあいだで起こらなくても、「母として息子にエロスを向けている」と考えられ、その状態を情緒的近親姦と呼びます。 後年においてフロイトは、エロスを「生の欲動」(独 Lebensteib)と位置づけ、「死の欲動」(独 Todestreib)であるタナトスと対峙させて考えました。(なお、それらは近年まで「生の本能」「死の本能」と誤訳されてきました。) そして1931年、『文明への不満』において、人間をふくめ生物はすべて、生の欲動によっていっけん物事を作り出し、建設していくかにみえるけれども、その深層はつねに、それをぶち壊し無に帰していこうとする死の欲動に裏打ちされており、人間という種においては、いわゆる文明が、人間を人間たらしめる創造と破壊の対象である、という世界観を述べました。 「それでは希望がない」などの理由から多くの人々から嫌われていますが、その世界観はその後さまざまな方面で発展されました。たとえばアメリカの哲学者マルクーゼはフロイトの考え方を一つの方向へ推し進めて1955年に『エロス的文明』を書き、1960年代の日本に大きな影響をあたえました。 |